子どもの不登校は、いまや特別なことではなく、多くの家庭が直面している問題です。
ニュースやテレビで取り上げられることも増えましたが、いざ「自分の子どもが不登校になった」とき、親としてどう向き合えばいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?
私自身も、4年前に息子が突然不登校になり、大きな戸惑いや不安を経験しました。
この記事では、不登校の子どもを持つ親としての体験談をもとに、同じ状況で悩む方へ少しでも参考になる情報をお伝えします。
息子の行動に違和感を感じた日

いつもよりずっと早く帰宅するようになった息子に、私は小さな違和感を覚えていました。
理由を尋ねても、はぐらかすように返される日々。
心の奥では「何かあるのでは」と気づきながらも、深く聞けない自分と親に素直に頼れない息子の当時の気持ちについて説明します。
息子の気持ち
後から息子に聞いたことですが、この頃は「まだ自分で何とかなる」「親には言いにくい」と思っていて、なかなか私に助けを求められなかったそうです。
友達のように何でも話せる親子関係を築けていると思っていても、思春期を迎えると「自立しよう」という気持ちから幼少期と同じように「なんでも話す」ということが難しくなってくるようです。
親の気持ち
「息子に何かあるのでは?」と心配しつつも、「思春期ならよくあること」「自分で解決できるはず」と軽く考えがちです。
思春期の子どもとの距離感は難しく、信頼関係を築くことが重要です。
無理に踏み込むのではなく「受け入れる体制」を整えましょう。
夏休みを迎えて

息子は2学期からますます学校へ行けなくなっていきました。
その頃、自分を立て直そうと必死になっていた息子が陥った状況について説明します。
オンラインで知り合った子への依存
何かに「依存する」のは、自分の意思や我慢ではコントロールできなくなってしまうので良いことではありません。
その頃、息子は自分の話を聞いてくれるオンラインで知り合った女の子に依存し始めました。
友達や親に相談できず、「不安」や「孤独感」が積み重なり、「落ちける場所」を探していたのだと思います。
しかし話せない状況が続くと更に不安になり、不安定になりました。
状況が良くならないことへの焦り
自分を立て直そうとしても改善しない状況に焦りを感じ始める息子はどんどん追い込まれていきます。
人は焦ると苛立ちを感じ、不快な状態になります。
このような状況で焦ることは状態を悪化させてしまうだけなので、周囲からのプレッシャーに注意が必要です。
誰かに相談することの重要性

誰かに相談するということはいくつかのメリットがあります。
- 気持ちが楽になる
- 解決の糸口が見つかる
- 孤独感の軽減
私は初めて直面した「不登校」について相談する決意をしました。
そこで私が得た2つの「気づき」を紹介します。
職場の上司への相談
まずは職場の上司に事情を打ち明けました。
すると意外にも、その上司の息子さんも長く不登校と引きこもりを経験しているとのこと。
診療内科にも通ったけれど大きな効果はなく、薬も依存の心配があるので注意が必要だと教えてくださいました。
助言をもらえたことはもちろんですが、それ以上に「身近に同じような経験をしている人がいた」という事実に、大きな安心を感じました。
オープンチャット登録
「不登校の子どもを持つ親限定」と書かれていて、普段は気にも留めていなかったものの、思わず登録してみました。
同じ悩みを抱える親たちが、毎日の子どもとの戦いの様子や、週末に少しだけほっとする瞬間、そしてその時々の気持ちを互いに書き込み、励まし合う姿がありました。
読むだけで心が軽くなる一方、「毎日こんなことを繰り返して、果たして改善できるのだろうか」という不安も生まれました。
理解し合えることは確かに心を支えてくれます。
でも、このまま何も解決できなければ、子どもも親も大変な人生を過ごすことになってしまうと強く感じました。
その頃の息子の状態
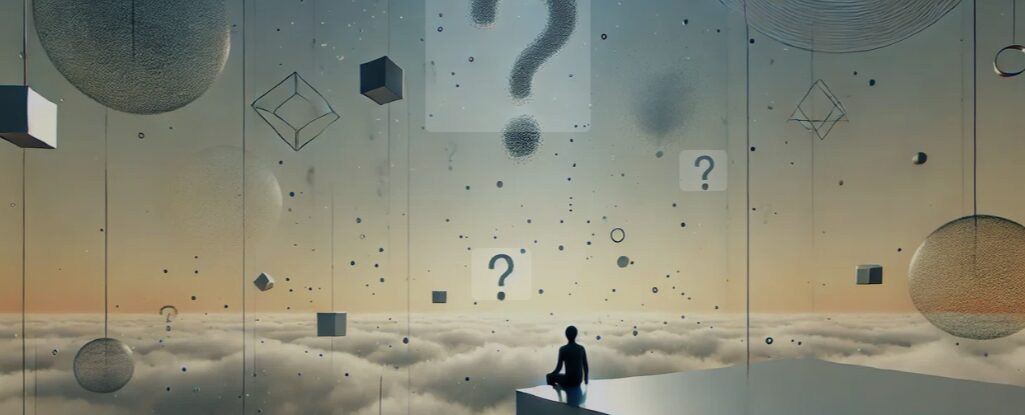
「学校に行かなければ」というプレッシャーが息子の心をさらに追い詰めていきました。
ここでは息子が最終的に陥った「状態」について説明します。
不眠
息子は「夜になるとドキドキして眠れない」と言い、眠れない日々が続きました。
無理に寝ようとしても眠れず、ようやく寝ても変な時間。
起きたらご飯を食べてまた横になる…そんな不規則な生活になっていったのです。
夜にしっかり眠ることは、心身の回復や免疫力の維持、ストレスの軽減に欠かせません。
だからこそ、夜眠れない息子は心も体も消耗しきっていきました。
自傷行為
不規則な生活が続くうちに、息子は自分でも止められずに腕を切るようになりました。
痛みに我に返ると私のところへ駆け寄り、「お母さん、またやってしまった」と訴えてきました。
不規則な生活は、自律神経の乱れに繋がり、気分の落ち込みや不安感を引き起こします。
睡眠不足は感情の不安定さやネガティブな考え方に偏りやすくなるので、不眠が原因で自傷行為に至ってしまったと考えられます。
薬
息子の希望もあり、処方薬は依存性が高いと聞いて不安だったため、まずは市販の精神安定剤を使うことに。
神経の高ぶりによるイライラや興奮感の鎮静、自律神経の乱れを整えてくれます。
また睡眠をサポートしてくれるものもあり、息子には合うのではないかと思い、与えることにしました。
ただし長期間の服用は依存性がでたり離脱症状がでるそうなので、やはり注意が必要です。
副作用もあるので、慎重に使用しましょう。
息子との接し方の変化
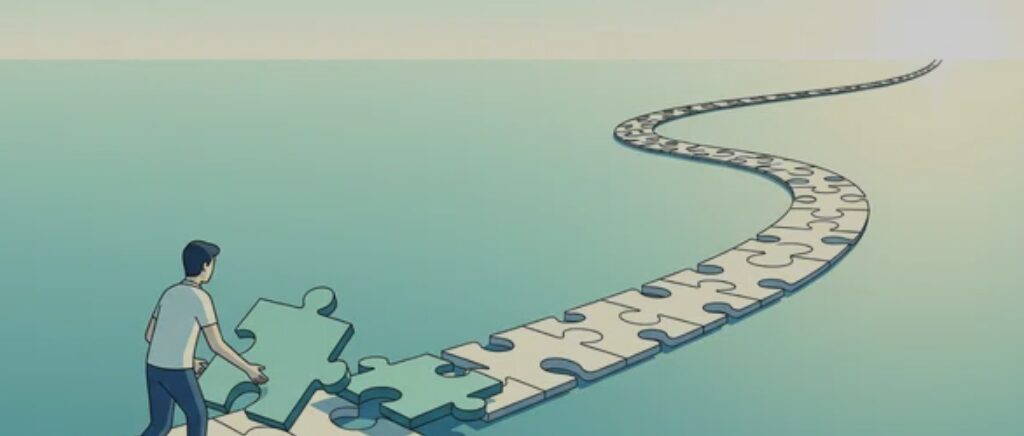
思春期の悩みだと軽く考えていたが、自傷行為が出たことで「今後」を真剣に考え、親子で立ち直る必要性を感じました。
命や心の安全が脅かされている状況では、「学校に行く、行かない」だけの問題では済みません。
高校を中退しても元気でいることが最優先であり、まずは心身の安定を取り戻すことが必要です。
ここでは私が行った、単純だけど大切なことをお伝えします。
会話
不登校や退学を否定せず、「急がなくていい」「いつでもやり直せる」と安心させることで、息子が自分の気持ちを話しやすくなり、回復への第一歩が生まれました。
否定や責めがあると心を閉ざしてしまうが、受け入れと安心を示すことで防衛心が解け、本音を引き出せるのだと私自身学びました。
「不登校でも構わない」「退学になっても問題ない」と伝え、自分のペースで立ち直る大切さをゆっくり話しました。
すると今まで言えなかった「申し訳ない」という気持ちを息子が口に出せるようになり、「もう学校には行きたくない」と正直に言えたことで本人も大きく楽になったと後で話してくれました。
運動
気分転換になり、夜もぐっすり眠れるようにと願い、一緒に体を動かすことに。
そのとき「バスケがしたい」と息子が口にした言葉に、思わず涙がこみあげました。
「何かがしたい」というその一言が、こんなにも前向きで力強いものだとは、これまで深く考えたこともありませんでした。
このとき、ようやく少し光が差し、出口が見え始めたような気がしたのです。
やはり体を動かすことは、ストレス発散や気分の改善、精神的な安定に繋がるので連れ出して良かったと思いました。
散歩
海辺で波の音を聞きながら歩く時間は、リラックス効果やストレス緩和、そして睡眠の質の向上にもつながるといわれています。
私たちはその散歩の途中で「不登校」や「将来」のことを話すわけではなく、ただ何気ない会話を楽しみました。
すると一時的に現実から解放され、まるで昔に戻ったような穏やかな気持ちになれました。
現実逃避なのかもしれませんが、精神的な休息にもなり、冷静さを得る効果もあるため、一時的な休息としては大切なことです。
現状打破するための行動

このままの生活を続けていても何も解決しないと思い、親子で話し合うことに。
「逃げ」ではなく「前向き」な行動であると思い、実践したことをご紹介します。
単位制高校への編入
現在の高校から単位修得証明書を提出し、編入先の高校で未修得の単位を取得することで「高卒認定」が発行され、大学や専門学校への受験資格が得られます。
息子は高校を中退し、足りない単位を単位制高校で補填し、卒業しました。
現在では不登校の生徒が増加しているため、高校生全体の約1割に相当する30万人が単位制高校に在籍しています。
不登校以外でも、自分のペースで学習することができるので選ばれることも多いようです。
一人暮らし
不登校や自傷行為、薬が必要なほど不安定な状態になってしまった息子でしたが、環境や気分を一変させるために一人暮らしをさせようと決意しました。
息子の可能性を信じ、見守っていこうと考えたのです。
環境を変えることは自己成長にも繋がり、モチベーションを高めます。
そして新しい環境におくことで、状況に応じた対応力や柔軟性を高めてほしいと願っての行動です。
まとめ

現在、不登校の子どもは約40万人とも言われ、その数は年々増え続けています。
「まさか自分の子どもが…」と、多くの親が突然その現実に直面します。
私自身もそうでした。
わずか一か月で5キロ体重が落ちるほどのストレスを抱え込み、親子で心身をすり減らした日々を今でも忘れられません。
ですが、その経験を周りに話してみると、驚くほど多くの親が同じ悩みを抱えていました。
皆、自分からは言い出せずに一人で苦しんでいたのです。
私が息子にしたことが正解とは限りません。
ただ一つ言えるのは、親自身が潰れてしまっては何も解決しないということ。
だからこそ、自分なりのストレス発散方法を持ち、子どもと向き合い、少しずつでも話し合うことが大切だと思います。
息子は完全に安心できる状態ではありませんが、それでも就職して1年半。小さな一歩を積み重ねています。
同じ悩みを抱える方へ
「思い切った行動には勇気がいりますが、子どもを少し信じてみませんか?
一歩踏み出すことで、これまでとは違う景色が見えてくるかもしれません。」
あなたとお子さんの未来が、穏やかで希望あるものでありますように。



コメント